2025年もいよいよ終わりが近づいてきました。
毎年お馴染みの台詞ですが、本当に時が流れるのは早く、年始めに立てていた抱負たちは何処へ、という感じですが…。
さて、今回は投資についてです。皆さんは「新NISA」活用できていますでしょうか?
私の話になりますが、積立NISAを2018年からちょこちょこ始めて、そのまま新NISAに移行していき、今のところ毎年の上限枠をフル活用しております。
現状、私は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 」(愛称:オルカン)と、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のどちらかを積立または一括で投資しています。
個人的にとてもシンプルで美しいポートフォリオなので、このままでも良いと思いつつ、もう少し攻めたいな…と欲が出てきてしまいました(よくないやつ)
ということで、来年からはリスクを管理しつつ、最大のリターンを狙うため、「コア・サテライト戦略」を取り入れた攻守ポートフォリオでいこうかなと考えています。
• コア 80%:(守り) 安定的な市場平均リターンを確保(オルカン or S&P500)
• FANG+ 15%:(攻め) テック企業の成長力を取り込み、資産の爆発力を追求
• 金ETFなど 5%:(保険) 株式暴落時のリスクを最小限に抑える守り
この記事では、この「80:15:5」の比率を、新NISAの「つみたて枠120万」と「成長枠240万」にどう振り分け、いつ、何を、いくら買うのかまで、具体的な行動計画として記します。
読んでくださっている方の中には「2026年が初めての本格的な投資になる」という方もいらっしゃるでしょうか。
年間360万円という巨大な非課税枠を前に、「何から始めていいかわからない」「失敗したくない」と感じる方や「自分もポートフォリオで悩んでいる」という方の参考になれば幸いです。
「コア・サテライト戦略」とは?

まず、「コア・サテライト戦略」について。
この戦略は、ポートフォリオを「コア(核)」と「サテライト(衛星)」の二層構造で構築するシンプルな手法です。
安定と成長を両立させる二層構造
① コア資産(守りの土台)
ポートフォリオの大部分(70〜90%)を占める「資産の核」です。
目的は、市場平均のリターンを確実に取り込むこと。新NISAの非課税メリットを最大限活かし、長期的な安定成長を狙います。
具体的には、全世界株式(オルカン)やS&P500のような、極めて分散が効いた低コストなインデックスファンドがこれにあたります。コアは一度決めたら、原則として放置です。
② サテライト資産(攻めと守りのアクセント)
ポートフォリオの一部(10〜30%)を占める「資産のアクセント」です。
目的は、コアだけでは得られない「超過リターン」の追求、または「リスクヘッジ」です。
私が今回選んだFANG+のような高成長セクターや、金(ETFなど)のような株式と相関性の低い資産がサテライトにあたります。
「流行りの個別株に飛びつく」「暴落時に全て売ってしまう」といった失敗は、コア資産という「揺るがない土台」を持つことで完全に防げます。
新NISA「80:15:5」比率の内訳

では実際に今回私が考える、新NISAの年間360万円枠を最短で最大限に活かすためのこの「80:15:5」比率についてです。
この比率には、「市場の成長を確実に捉えつつ、テックの爆発力を引き上げ、万一の暴落に備える」という意図があります。
| 投資対象 | 比率 | 新NISA年間投資額(360万円換算) | 役割と期待効果 |
| コア:オルカンまた はS&P500 | 80% | ¥2,880,000 | 守りの土台。市場平均を確実に得るための安定成長。 |
| サテライト(攻):FANG+ | 15% | ¥540,000 | 攻めのアクセント。高成長セクターによる超過リターン追求。 |
| サテライト(守): 金(ETFなど) | 5% | ¥180,000 | リスクヘッジ。株式暴落時における防御力と心理的安定。 |
| 合計 | 100% | ¥3,600,000 |
なぜ「80:15:5」なのか?
資産の大部分をリスクの低いインデックス(オルカンやS&P500)に任せることで、精神的な安定と長期的な複利効果の最大化を狙います。この土台が崩れない限り、資産は着実に増え続けるはず。
攻めすぎるとリスクが高まりますが、コア資産で守りを固めているため、全体の15%程度を「iFreeNEXT FANG+インデックス」のようなハイリスク・ハイリターン商品に賭けたいなと。この15%が、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを引き上げてくれることに期待。
資産の5%程度を「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)」などの「金」に振り分けることで、株式市場がパニックに陥った際の「保険」となります。金は株と逆の値動きをすることが多いため、分散効果を狙う。
【守りの土台】コア資産80%(288万円)

「80:15:5」戦略において、最も重要なのが、コア資産80%(年間288万円)の部分。ここはしっかり押さえておきたい。
非課税枠の「つみたて枠(120万円)」と「成長枠(240万円)」をどう組み合わせるか、整理します。
つみたて枠120万円は「これ一択」
新NISAの「つみたて投資枠」は、年間120万円。これは、毎月10万円を自動で積み立てていきます。そして、投資対象は迷いません。
選ぶべきは、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」か「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のどちらか。
- オルカン:世界中の株式に分散投資し、特定の国に依存しない究極の分散と安定性を重視したい人向け。
- S&P500:世界経済を牽引する米国トップ企業500社に集中し、高い成長期待を重視したい人向け。
どちらも業界最低水準の信託報酬で、長期投資に最適な商品です。このどちらか一本に絞り、毎月10万円の自動積立を設定することで、つみたて枠は完璧に使い切れます。
私はなんとなくでしかないですが、米国一強に少し懐疑的なので、単純な「心地の良さ」からオルカンにしようと考えています。
「ベストな買い方」は一括か、分割か?
年間360万円を使い切るには、残りの成長投資枠240万円から、コア資産として168万円をさらに購入する必要があります。(360万円×80%=288万円−120万円=168万円)
ここで問題になるのが、「168万円をいつ買うか」です。
結論、「年間の早い段階での一括投資」をします。
統計的には、投資期間が長くなるほど、時間を分散させる積立よりも、早く非課税の恩恵を受けられる一括投資の方が期待リターンは高くなる傾向があるみたいです。
正直、抵抗があるかもしれませんが、「非課税期間を少しでも長くする」という戦略的視点でここは一括を選択。
大きな額を一括で投じるのが心理的に不安であれば、168万円を毎月14万円ずつ(12ヶ月)に分けて購入するなど、ストレスにならない範囲で分割しても問題ないかなと。
コアは「長く持ち続けること」が最も重要と考えます。
【攻めの要】サテライト資産20%(72万円)の具体的な狙い
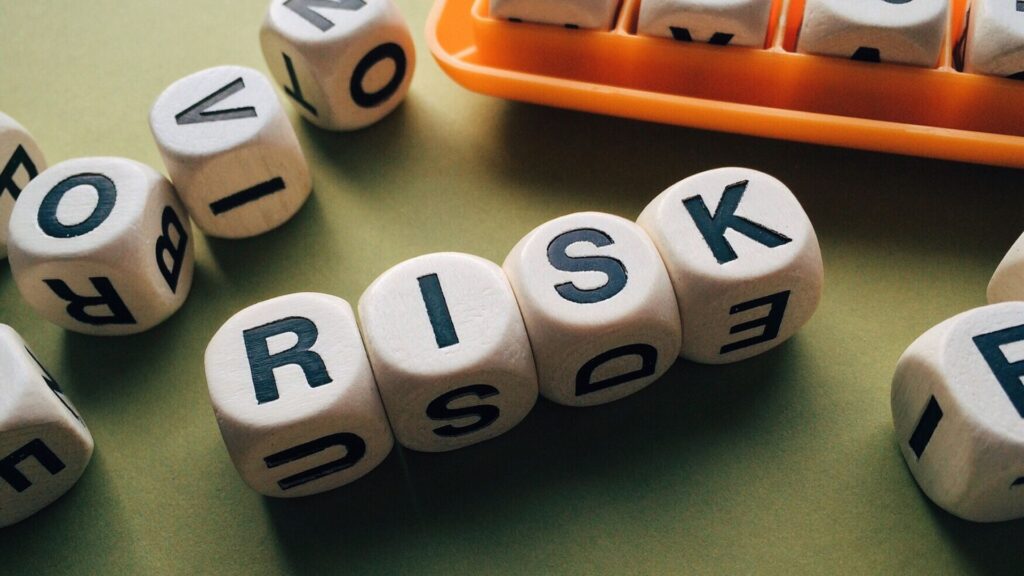
コア資産で守りを固めたら、いよいよ成長投資枠の醍醐味であるサテライト資産の出番です。
サテライト枠は、コアの安定性を崩さずに、全体のパフォーマンスをブーストさせる「攻め」と「守り」のアクセントに徹します。
爆発力15%:FANG+で高成長セクターを取り込む理由
私がサテライトの「攻め」の柱に据えるのが、「FANG+(iFreeNEXT FANG+インデックス)」(15% / 54万円)です。
なぜ、S&P500やオルカンで十分なのにFANG+を選ぶのか? その答えはシンプルに「超過リターン」を狙うため。
FANG+は、NVIDIA、Apple、Amazonなど、世界的なイノベーションを牽引する厳選された約10社の巨大テック企業で構成されています。
S&P500もテック企業比率が高いとはいえ、FANG+はさらにその中でも集中投資することで、これらの企業の爆発的な成長をダイレクトに取り込むことができます。
高いリターンが期待できる反面、価格変動も非常に大きい「ハイリスク・ハイリターン」商品です。
しかし、資産の80%はすでにコア資産で守られています。
この15%という比率なら、仮にFANG+が大きく下落しても、ポートフォリオ全体への影響は限定的です。
リスクを限定した上で攻めの要素を組み込みます。
防御力5%:金が暴落時に果たす「保険」の役割
そして、もう一つのサテライトが「守り」の要、金(5% / 18万円)です。
金は、「株が下がると金が上がる」という株式との相関性が低い特性を持っています。
戦争や経済危機、高インフレなど、株式市場がパニックに陥った際、投資家は「安全資産」である金に資金を移す傾向があります。
この5%は、ポートフォリオ全体に対する「保険料」と考えます。
株式市場の大きな暴落は心理的なダメージが非常に大きいです。
しかし、金が暴落時に値上がりすることで、全体の下落幅を緩和し、「パニック売り」を防ぐための心理的な支えになってくれることを狙います。
成長投資枠で購入できる国内の金連動型ETFなどを選ぶことで、手軽にこの防御力を手に入れることができます。
【行動計画】2026年、新NISA枠360万円を使い切るロードマップ

これまで解説した「80:15:5」の黄金比率を、新NISAの年間360万円枠に当てはめて、2026年に迷いなく行動できる具体的なロードマップを示します。
ステップ1:つみたて枠の設定(最優先事項)
| 項目 | 金額 | 投資対象 | タイミング |
| つみたて枠満額 | 月100,000円 | オルカン or S&P500 | 2026年1月より開始 |
まずは証券口座で「つみたて投資枠」の設定を完了させます。
毎月10万円が自動で引き落とされるように設定すれば、年間120万円の非課税枠が自動で埋まります。
私は現在、SBI証券+三井住友カードでクレカ積立しているので、毎月10万クレカ積立設定したいと思います。
ステップ2:成長枠でのコア資産の購入(土台の確定)
| 項目 | 金額 | 投資対象 | タイミング |
| 成長枠 コア | ¥1,680,000 | オルカン or S&P500 | 2026年1月〜3月推奨 |
つみたて枠を設定したら、すぐに成長枠でのコア資産(168万円)の購入に移ります。
360万円 = 288万円 – 120万円 = 168万円
前述の通り年間の早い時期(1月〜3月頃)にできるだけ一括購入をします。非課税期間を最大限確保し、複利効果を最大化するためです。
ただし、ここはストレスにならない範囲で分割してもいいかなと。
ステップ3:サテライト資産の分散購入(爆発力と保険の確保)
| 項目 | 金額 | 投資対象 | タイミング |
| サテライト FANG+ | ¥540,000 | FANG+指数連動商品 | 2026年 上半期 |
| サテライト 金ETF | ¥180,000 | 国内金ETF | 2026年 通年 or 株式高値時 |
残りの72万円をサテライトに充てます。
- FANG+:コア資産(168万円)の購入が完了した後、上半期の早い段階で買い付けを完了させる。
- 金:これは保険です。株式市場の様子を見ながら「少し高値圏に来たな」「不安要素が増えたな」と感じたタイミングで、数回に分けて購入するのがよさそう。
この3ステップを完了させることで、新NISA枠360万円を、戦略的にそして効率的に使い切ったことになります。
まとめ:新NISAで最高のスタートを切る攻守ポートフォリオ
2026年の新NISAで最高のスタートダッシュを切るための勝てるかもしれない?戦略を解説しました。
ここで、「攻守最強ポートフォリオ」の核となるポイントを再度確認しましょう。
- コア・サテライト戦略:安定(80%)と、攻め・守り(20%)の役割を明確に分ける。
- 黄金比率「80:15:5」:オルカン/S&P500で守りを固め、FANG+で成長を狙い、金で防御力を加える。
- 行動計画の実行:まず「つみたて枠120万円」を自動設定し、次に「成長枠」で残りの資産を一気に構築する。
参考になれば幸いです!
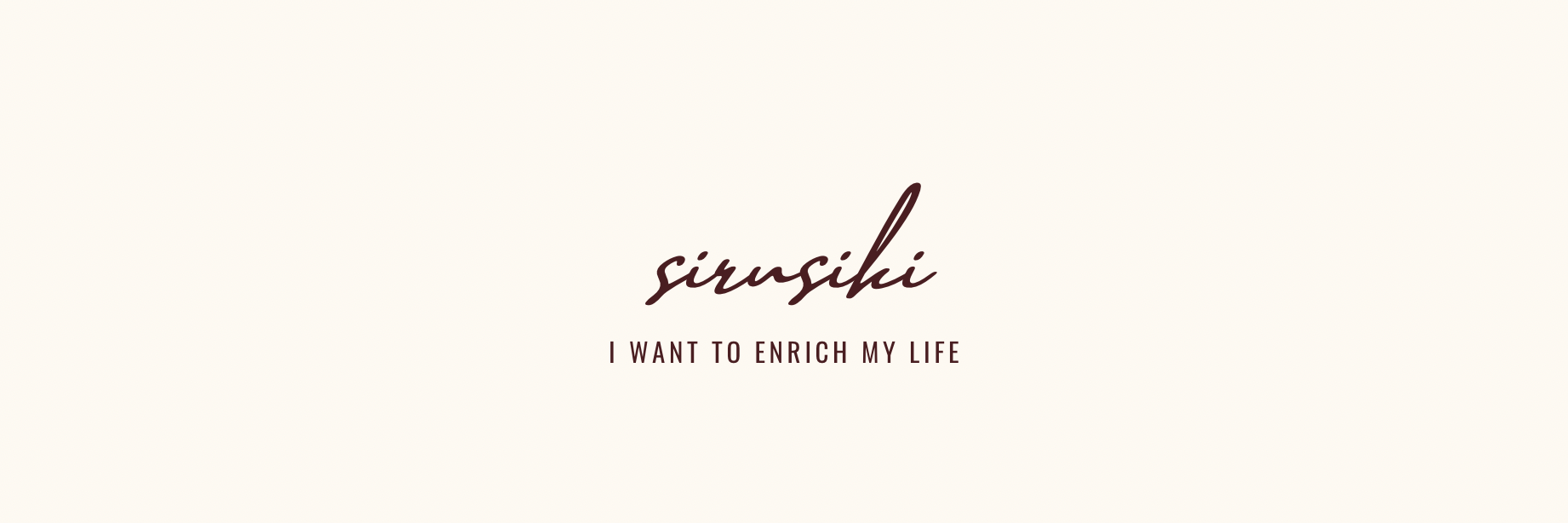


コメント